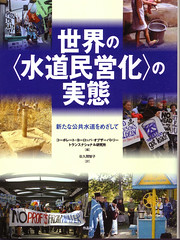May 2007アーカイブ
でも、いちおう検索してみたところ出てきた京都新聞の記事によると
中国原産のチュウゴクオオサンショウウオが京都市左京区の鴨川上流でも野生化している可能性の高いことがわかった。国の特別天然記念物で日本在来のオオサンショウウオと同属。生態が似ており、互いに駆逐しあったり交尾したりする危険性がある。西日本各地の川でも見つかっており、専門家は京都府などに対し、駆除などの対策を早急に取るべきだと訴えている。[read more]
ってことで、天然記念物ではなかった可能性高し。
・「動けば変わる。生きるって楽しい、と思える日本へー龍平と応援する人々の基本政策集」([全文](PDF)
表紙には次のように書いてあります。
《お読みになる前に》
● この「龍平と応援する人々の共同マニフェスト(案)」は、未完成のものです。
● 完成させるためには、「あなたの提案」が必要です。
● 付け加えたい提案がある場合は、
提案することを【問題点】と【解決策】に整理してお寄せください。
● 文章を修正したい、あるいは削除したいという提案がある場合は、代案となる文章をお寄せください。
● 提案者が議論できる場を、別途設けます。
● できる限り多くの「提案」を含めたいと考えていますが、他の事柄との矛盾や考え方の相違によって、採用できない場合があることをあらかじめご了承願います。
《提案の送付先》
川田龍平を応援する会共同マニフェスト係
郵送の方: 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-18 オオノヤビル5 階
FAX の方: 03-5369-1474
メールの方: office@ryuheikawada.jp
※ 必ず提案者の「お名前」と「ご連絡先」を明記してください。
ご連絡を差し上げる場合がございます。
で、「提案者が議論できる場を、別途設け」るという部分のワークショップでファシリテーターを担当することになりました。
会場のキャパシティや「ワークショップ」として成立する人数という限界もあるのですが、ご意見を寄せて頂いた方はなるべく参加してもらうような設計で行きたいと思っていますので、みなさんの「政策」を「川田龍平を応援する会」までよろしくお願いします。
私としては、有権者が「4年ないし6年に一度の王様」であるのではなく、コンスタントに政治に関わり、意見を出していくような(やや雑ぱくに「参加型民主制」と纏められるような)システムを作っていくことに関心があります。
で、そういった関心に応えてくれたのが以前からの友人である川田君の陣営だったと言うことでして(まぁ、グローバリゼーションの問題なんかについては政策そのものにもだいぶ意見を聞いてもらっているので、それなりに関係は強いわけですが)将来的には他の候補、特に既存政党の候補にも使ってもらえるような政策討論ワークショップをつくっていきたいなぁ、と思っていたりします(なので、他の候補からも声をかけて頂けるのはいつでも歓迎。ただ、利益相反になるのも拙いので、参議院東京選挙区については今回は川田龍平に絞らざるをえないと思いますが…)。
【追記】
これ、よく見るとご意見締め切りが書いてないですね。
基本的には随時受付と言うことになるかと思いますが、ワークショップに参加して頂くには6月5日ごろまでに意見を出して頂けると(人数等調整の上)選挙事務局からご連絡が行くという形になるんじゃないかと思います(現在確認中)。
【追記2】
ウェブサイトにはすでに掲載されていますが、締め切りはやはり5日とのことです。時間が短くて申し訳ありませんが、是非ご意見をください。
初乗り(ゾーン1内の場合)で4ポンド(約960円)という、何故それで暴動が起こらないんだ、という料金。
ところが、最近はみんなオイスターカードという、日本のSuicaのようなカード(もっとヘナヘナで壊れやすそうですが)を持っていて、それを使っている。
日本のSuicaはまったく割引なしで、割引のある私鉄カードでもせいぜい5パーセントですが、ロンドンではオイスターカードを使うと、なんと初乗り1.5ポンド(360円)。
とうてい「安い」と言える金額ではないにせよ、まぁ、世間の常識の範囲内になんとか収まっている感じです(バスなんかもそんな感じで安くなります)。
この事実に気がついたので、とりあえず一枚入手してみました。
どうも、ヨーロッパはなにも知らない観光客からぼったくるといううことなのか、こういう「知らないと大損する」理不尽な料金体系が多い気がします。
あと、バスは社内ではお金を払えないようになっていて、そのかわりバス停には券売機が設置されているのですが、これもお札は入らないし、コインも全種類受け付けてくれるわけではない。
日本だと基本的に機械化されればそのぶん便利になって、多少でも使い勝手が悪いと交通機関は大きな批判を浴びますが、どうもヨーロッパでは全体に機械化すると消費者にとっては面倒になります(地下鉄の自動改札も日本のようにスッとは開いてくれないので、日本と同じ感覚で通り抜けようとすると、だいたい激突することになる)。
ヨーロッパ人が全般にテクノロジー嫌いなのはこのへんにも理由があるのかも知れません。
ちなみにオイスターカードを初めて作る際にはデポジット3ポンドが必要。
これらはクレジットカードでも払えます(このあたりもSuicaと違いますね)。
また、登録すればサイトからチャージしたり、無くしたときの処理も可能みたい。
詳細はTransport for Londonで
昨日、イギリスから帰国しました。
やや時差ボケ気味です。
帰国前日、たまにはと思い、パディントン駅の前のステーキ屋(アンガス・ステーキハウス)に入ってみました。
(イギリスだと諸事、物価が高いわりにあまり美味しくないので一人だとあまりたいしたものは食べないので…)
味としてはコクがあって、たしかに美味いのですが、兎に角固い。
しかも、バカでかいので、食べ終わるまでにはアゴが疲れてしまうと言う…。
イギリスで美味いもの食べるのはなかなか大変です。

ゴールデン・ウィークもあけて、なんとかADB京都総会・市民フォーラムも全日程を終了である。
国際機関の総会に合わせてNGO集会を開くというのは、国際的には一般的になっているが、日本でこれだけ大規模に行えたのは初めてのことだと思われるので、この点、評価できよう。
最初のうちはやや妖しかった主催団体や参加団体相互の連絡も、最終的にはかなりスムーズになったという実感があるのではないかと思う。
たぶん、最初のうちはアジア開発銀行に対してどこまで否定的な論調を出していいものか、各団体ともやや決めかねていたのだと思われるが、海外団体からの要請(是非デモをさせろとか…)などもあって、結果的にはADB総会との対立軸が明白になって良かったのではないか。
中途半端な議論をするよりも問題の軸ははっきりすることで議論は促進されるし、メディアにも取り上げられやすいというポジティヴな副作用もある。
実際、いくつかの新聞が取り上げてくれたようである。
・ADBによる開発問題を考える 環境NGOら 同大でシンポ(京都新聞)
・アジア開銀年次総会NGOが対抗シンポ(読売新聞)
・ADB総会:"京都デー" 光と陰と 伝統・革新PR/NGO「施策で悪影響」(毎日新聞)
・アジア開発銀行年次総会で「京都デー」 市内ではNGOがシンポ(産経新聞)
※いずれも地方版ではあるが、読売はデモの様子まで含めて取材している。一方で朝日は記事なしってのは、どういうことだ!?
5日のシンポジウムはかなりの大入り(250〜300人ぐらいか?)だったわけだが、中には、「ADBってなんだか分からないけど、新聞で騒いでいるし、40周年だと言うからちょっと参加してみるか」というような「普通の人」層もだいぶ混じっていたようである。
そういう人には(特に日本的感覚からすると「40周年でお祝いだと言ってるのにネガティヴなことを言う」ことに)違和感の残る集会だったような気もする。
開場からの質問用紙には、特に、全ての第三世界債務は正統ではない(Illegitimate)であると論じたジュビリー・サウスのリディ・ナクピル氏に対して「悪いところばかり取り上げるが、いいこともしているのではないか?」という質問が集中したようである。
もちろん、バングラデシュのフルバリ炭坑開発の事例ではデモ隊への発砲で死者まで出しており、そのことを報告した論者がいる前で「文句ばっかりいってるんじゃないか?」と質問してしまうと言う「ブルジョア的冷酷さ」(…久しぶりに使ったな、この言葉)には不快感を禁じ得ないが、一方でそういった聴衆を納得させる論旨ももう少し必要であったという気もする(「よいこと」のアピールに関してはADB自身や日本政府がもうちょっとまじめにやった方がいいと思うんだけどね。アジア各地で無駄な「公共事業」を続けているという事実が明るみに出るのが怖くてやれないのだろうか?)。
ADBや世銀、各国のODAが抱える問題は二つあって、一つは汚職や独裁者を支援するような開発(日本は特にインドネシア、フィリピン、ビルマ等への援助で悪名高い)や環境破壊をもたらすような開発の問題である。
これはマスメディアに衝撃的に取り上げられることによって印象深い(デモ隊への発砲、なにもないジャングルにそびえ立つさび付いて使われていない発電所、ダム建設で先祖伝来の土地から追い立てられる先住民、と言った図はメディア的に「美味しい」素材であろう)。
しかしながら、より本質的な問題は、先進国型のインフラ開発と自由貿易による発展という開発モデルが第三世界においても望ましく、かつ可能(より本質的には持続的なものとして可能)かという問題である。
恐らく、前者の問題は後者の問題の従属項にすぎず、本質的な問題は世銀やADBの設立および運営ポリシーにあるのであろう。

さて、ではADBのような機関は今後「粉砕されるべき」かというとここで議論は分かれる。
たとえば、ADBの総会の折にはASEAN+3の蔵相会議も開かれる(要するに看板が掛け変わるだけでメンツは同じだから)のだが、京都では昨年の会議(南インドの都市ハイデラバードで開かれた)で提起されたアジア通貨基金構想に近いものが実施されることがほぼ決まったようである。
これは恐らく、短期的にみればアジア経済の安定に貢献するのであり、おそらく貧困層に対しても一定の恩恵がある(通常、先の記事でもパトマキ氏の言葉として述べたとおり、変動相場制の利益をより多く享受するのは投機的取引を行える富裕層である一方で、いったん通貨危機が起これば被害は貧困層の生活に直撃する)。
したがって、ATTACとしてもこの結論は歓迎声明を出すべきことがらに見える。
地域ごとに通貨統制能力が高まることは、おそらく通貨取引税などの導入の弾みにもなるということもあるかも知れない。
しかし、開発インセンティヴを強化し、第三世界をグローバル経済により強く組み込むことが問題である、という先の立場からすればこれは大いに問題である、と主張することはできるだろう。
このあたりで、「オルタグローバル派」の即席の連帯はやや先行きが怪しくなるのである。
「ADBって食べられる?」という無関心層にどのようなアピールをするかということと、こういった議論をある程度つめていくかということは割と深刻な問題であろう。
余談だが、アジア通貨基金構想は90年代に日本と東南アジア諸国(特にマレーシア、シンガポール)が積極的に推進し、アメリカに粉砕された計画そのものである。
こういうことが(ハイデラバードでは主にインドのイニシアティヴで)可能になってきたというのは、印中をはじめとした第三世界諸国(の一部)の発言力の増大と、アメリカの世界支配能力の凋落を印象づける(朝日新聞の報道ではピール米財務次官補代理が「ADB、ミニIMFになる必要ない」と述べており、やっぱり嫌がってはいるようである)。
90年代の「敗戦」以降、日本のエスタブリッシュメントはアメリカに抵抗する意志をすっかり失ってしまっているようであるが、この先どのようなタイミングで世界政治に復帰するか、大きな課題であろう(とかいうと右からも左からも嫌われるのであるが…)。
ゴールデンウィーク期間中、京都の北にある国際会議場ではアジア開発銀行の年次総会が開かれている。今年はアジア開発銀行40周年だとかで、それなりに気合いが入っている。
この手の国際機関の総会のさいには、グローバルな抗議集会が行われるのが通例となっているわけであるが、日本ではこれまで色々な問題からそれが難しかった。今回は、これまでにない規模でアジアを中心とした各国からの社会運動家が来日している珍しい機会となった。
で、とりあえず4日にATTACが中心となって行ったシンポジウムの速報。
ちなみに、春日個人による個人的な報告であるとお考えください(ATTACとしてはそのうちなんかつくるでしょう)。
2007年5月4日13時から17時、京都市内にあるハートピア京都にて『通貨投機・金融自由化に対抗する: アジアのネットワークを』というシンポジウムが開かれた。これはアジア開発銀行京都総会に合わせて行われている『アジア開発銀行京都総会・市民フォーラム』(5,6日、於同志社大学)の一環として行われたものであるが、スピーカーの都合などから日程をずらして行われたものである。主催は「国際通貨税ネットワーク」となっているが、これは通貨取引税(Currency Transfer Tax 以下CTT)を求める国際的なネットワーク運動の呼称であり、実態としては日本ではATTAC Japanおよび各地のATTACなどが担っている。 講演はATTACフィンランドのヘイッキ・パトマキ(ヘルシンキ大学政治学部教授)およびカタリーナ・パトマキ(グローバル民主化ネットワーク研究所)、京都大学の諸富徹氏(京都大学大学院経済学研究科助教授)によって行われ、その後3人の海外参加者から短い報告があり、最後に総合討論が行われた。 ヘイッキ・パトマキ氏およびカタリーナ・パトマキ氏はご夫婦であるが、それぞれの立場でATTACの活動に取り組んでおり、ヘイッキ氏からはつCTTについて、またカタリーナ氏からは第三世界の債務の問題について講演が行われた。ヘイッキ氏はまず、CTTという概念の歴史的経緯について概括した。
CTTはトービン税と呼ばれることもあるが、これはケインズ派の経済学者ジェームズ・トービンが提唱したことによる。トービンは、現在国際社会で議論されているCTTに自分の名前を冠されることを嫌ったが、いくつかの大きな通貨危機のあと、CTTへの注目は増大している。特に、1997年のアジア通貨危機は一つの転機になり、欧州各国では2000年前後にいくつかの国でCTT法案が議会を通過している。
また、ブラジルのルラ大統領とフランスのシラク大統領によって提唱された国際的なイニシアティヴでは、貧困削減のためのミレニアム開発目標の実現のために、国際課税が推進されることを推奨している。ミレニアム開発目標の実施には年間500億ドルの資金が必要であり、この資金を国際課税で捻出すると言うことが推奨されている。
現在、国際的なNPOなどにとっては、この後者の意味でのCTTが重要性を増している。もちろん通貨及び国際金融の安定を、よい副作用と位置づけることはできる。また、公正さ(Justice)という問題もある。国際金融における投機的なマネーは人々の生活を不安定化する一方で、一部の人間にだけ莫大な利益をもたらす。いわば、「利益が個人化され、リスクは社会化される(Privetise Benefit, Socialise Risk)」のである。このリスクを裁定するための資金を課税し、グローバルな共有材のために利用するという考え方は、公正さの概念にかなうであろう。加えて、通貨取引への投資を規制することで、金融セクターに回っていたお金が実体経済への投資に回るという効果も期待できる。
最後に、国際金融の統制というのは、新たな経済民主制への挑戦でもある。資金をどのように使うかなど、単に国家レベルでの民主制ではない、国際的な機構を民主的に運営するようなシステムが必要である。これについては詳細に触れる時間はないが、ウェブサイトで"Draft Treaty on Global Currency"が公開されており、日本語でも読むことができるので参照して頂きたい(注1)。次に、カタリーナ氏は今なお第三世界債務の問題は非常に大きく、その問題性は増大してさえいると述べた。
債務問題は多くの問題の複合体であり、貧困やHIVなど多くの問題に取り組む第三世界のNGOの多くが債務問題についてある程度関係し、その完全な帳消しを求めている。債務は第三世界の国家予算、特に公共サービスセクターを圧迫することによって他の諸々の問題の解決を難しくしているのである。
2000年に行われたジュビリー2000キャンペーンでは、ヨーロッパでも債務帳消しが「チャリティ」なのか経済的な公正さと効率性の問題なのか、という点が大きな議論になり、それが運動分裂の原因にもなったと述べた。その上で、第三世界債務の問題をグローバル経済の問題として位置づけ、理解していくことは今後の世界にとって重要であると述べた。
1982年のメキシコ危機のころから、債務の問題は注目を集め、ジョゼフ・スティグリッツ、ジェフリー・サックスやポール・クルーグマンといった著名な経済学者たちがこの問題に取り組み始めた。これらの論者は債務帳消しがグローバル経済にとって必要であり、かつ好ましい結果をもたらすと論じている。
また、国際的な市民社会組織(CSOs)の合意としては、債務問題がグローバルな経済構造、特にブレトンウッズ体制が未完成のままいくつかの問題を積み残し、GATTなどの修正案がそれを解決できなかったことの帰結である。こう考えれば、債務問題は第三世界に責任があるのではなく、先進国も含めた地球全体の問題であることはあきらかであろう。
しかし実際は、債務削減/帳消しは経済学の用語で語られるが、基本的には政治的な動機で行われてきた。ドイツの債務削減はナチスの再興を防止するという名目のために行われたし、エジプトのケースでは湾岸戦争への協力の見返りとして行われた。最近では、イラクの債務帳消しが米国の影響下にある新体制を支援するために行われたことは記憶に新しい。
債務についての研究はまだ30年に満たず、多くの問題が積み残されている。今後議論して行くべき問題が多く残っている。これらはもちろん、経済だけではなく、法的、政治的側面から総合的に行われるべきである。また、帳消し後に再び重債務化が起こらないようにする方法はあるかや、国内的にどのような制度を作っていくかを論じる必要もある。国連貿易開発会議(UNCTAD)は第三世界の多くの国の経済状態が悪化することにより、重債務化が激化する可能性を指摘している。
IMFは支払い能力や正統性の低下により、国際社会でのプレゼンスを低下させている。最近、ベネズエラはIMFからの脱退を表明した。一方で、新たな貸し手が台頭している。民間資金や中国に代表される新興国である。これらの資金源は融資の条件が緩く、高金利であるという特徴がある。この影響を考えることも重要である。
当面の目標としては、債務帳消しの完全な実施を求めること、その運動を社会的公正を求める第三世界の社会運動や、より広い意味での「オルタモンディアリズム運動」と連携させること、そしてそれらをグローバルな民主化を求める運動とつなげていくことが重要である。最後に、諸富氏からは環境税との関連でCTTの合理性と必要性が述べられた。
ドイツで、租税の本質から外れるとして、環境税に対する違憲訴訟が行われたが、ドイツ最高裁の判決はこれが合憲であるというものであった。これを考えれば、CTTも認められる素地はあると考えられる。しかし、経済学者のピグーが環境税を提唱したのが1920年代のことであり、最初の環境税がオランダの下水課税であり、1969年のことである。このことを考えれば、こうした概念の浸透に時間がかかるのはある程度仕方がない。
また、環境税はこれまでのところ国家レベルの課税として実施されているのに対して、CTTは国際課税であり、より制度的に複雑であるという問題がある。ただし、炭素税に関して言えば現在までのところ国家レベルで実施されているが、いずれにしても国際的な制度は作らなければ行けないので、この点はCTTだけの問題ではない。
やはり、公正さという問題を私的なリスク(Private Risk)と社会的なリスク(Social Risk)という問題でとらえる必要がある。トレーダーは私的なリスクをあおり、結果として社会的なリスクにつながる。この社会的なリスクを経済の外部性(Externality)あるいは社会的なコスト(Social Cost)と考えれば、課税は可能であろう。このことは、汚染者負担の原則(Polluter Pays Principle)あるいは受益者負担原則(Benefit Principle)というところから議論を進められると考えられる。後者の場合、取引額ではなく、収益への課税が好ましいと言うことになろうが、技術的にはそのほうが遙かに困難である。
また、税制の共通化(Tax Harmonization)への要求は高まっており、実際EU圏内では具体的な作業が進んでいる。しかし、税制の共通化は一国でも反対すると成立しないため、様々な困難がある。とはいっても、自国の税率を低くして企業を誘致するということを相互に行う租税競争所帯が長期に続くことは問題が大きいので、これは解決すべきだし、するべき問題である。また、単に収入を国際機関にゆだねるのではなく、民主的に議論するための制度が必要になってくるだろう。これら三者の発表を受けて、各国からいくつかの報告が行われた。
韓国からは米国資本(ローンスター銀行)が国営銀行の一つを買収したのだが、そのときに粉飾会計を行って買収金額を下げ、3年後に3倍以上の高額で別の国営銀行を含む二つの韓国系銀行に売り抜けたという事例が紹介された。
フィリピンからは、国家予算の半分が債務返済のために使われ、公共サービスが著しく制限されている状況が報告された。また、恒常的な関税引き下げ圧力や、日比FTAを含む自由貿易協定により、租税歳入が低減しており、そのために付加価値税の増税などが行われている現状も指摘された。
また、フィンランドからは、こうした状況をふまえて、WPF(World Public Finance)キャンペーンの必要性と現状が報告された(注2)。世界社会フォーラムなどの機会に発議され、CTTの導入やタックスヘブンの規制などを訴えていく国際的なキャンペーンである。特にタックスヘブンの問題は深刻であり、IMFの統計でも途上国にはいるべき税収のうち少なくとも5千億ドルが世界で70カ所ほどあるタックスヘブンに逃げていると考えられるという。この後、質疑応答が行われ、日本からもこういった政治、経済と南北問題の公正を求める運動に積極的に参与していくべきであるという主催者側からの提起などが行われた。
前からちょこっとお手伝いしていた本『世界の〈水道民営化〉の実態: 新たな公共水道をめざして』が出版された(昨日入手)。
オランダのNGO、トランスナショナル・インスティテュート(TNI)とコーポレート・ヨーロッパ・オブザーバトリー(CEO)で原書の発刊にも係わっていた(我が友人であるところの)岸本聡子・山本奈美両氏が編集をしている、極めて正統性、信頼性の高い翻訳である。
ちなみに原書はブラジルとインドで行われた世界社会フォーラムに集まった水問題に関する活動家が、各地の問題を報告する中で生まれた本であり、社会フォーラムの「個別の運動をつなぐネットワークの形成」という側面の最大級の成果の一つであると言える。
地図をつくったり(書籍に載っているものの大元を下に置いておきます。やっぱプロは綺麗に仕上げるよね)、ケララとフランスのところを下訳したりしているので、ご紹介。
あと、写真も若干提供していて、例えば45ページがこちら(ケララ・オラヴァナの井戸)。
ちなみに下訳については翻訳者の佐久間さんに「多少は役に立ちましたか?」と聞いたところ「水問題に関係しないところは修正不要だったから…」という主旨のお返事が返ってきた orz
(でもね、言い訳すると特にフランスの章は専門用語が多くて、しかも微妙にフランス語の直訳なので、ニュアンスが読み取りがたいんですよ)
ここでも昨日の記事で触れたPublic/Privateと公/民の対立軸のずれの問題は顕在化してきて、「公営水道」というと巨大で不効率なものを想起させ、「民営」というとなにかよいものを指すような気がする。
一方英語で「民営化」はPrivatization(私営化・私有化)なので、もともとからしてやや強欲さを感じさせるイメージの言葉になっている。
政治的文脈に於ける「公益対私益」の対立では公益に有利で、経済的文脈に於いては「公営対民営」で私益に有利という、欧米よりもレーガン的なネオリベラルに有利な言語構成になってしまっているところが問題なわけである(このあたりを脱構築できないと日本の左派に未来はないんじゃないだろうか…)。
もちろん、実践的な局面では「巨大で不効率な公営に対して素早く消費者のニーズをくみ取る民間」というイメージは各国共通のもので、それがいかに裏切られ、そこからいかにしてもう一度(たぶん真の意味で)公的なものを再構築していくか、というのが本書の各章で述べられているわけである。
日本は「水と安全はタダ」と言われ、水道に対する危機感は非常に薄いと思われるが、公共空間についての議論にも資するであろうし、是非いろいろな立場の人に読んで頂きたいものである。
ということで、みなさん、水と公共性は大切に…。
以下、目次。
憲法記念日もあと一時間を残すのみですし、そもそもこの議論に参入すること自体がいまさらの気もしますが、一応。
まず憲法を改正すると言っても大きく分けて二種類会って、アメリカなどがよくやるように修正条項(Amendment)を付加していくという方法と、文面を全面的に変更するという方法があり得る。
「これまで我々の行なってきた全ての改革は、昔日に照らすという原理の上に立っている」というエドマンド・バーク的な(たぶん極めて健全な)保守主義に照らせば、前者のほうが国民国家としての連続性を維持できるという観点から極めて好ましいはずである。
実際、全面改正を行ってきたのは基本的に急進主義左翼政権であり、保守政権が全面的な憲法改正を行ったという事例は近代史にはあまり見いだせないはずである。
近年では、ベネズエラのチャベス政権が国名の改変を含む憲法改正を行っている。
しかし、日本の保守政党である自民党による憲法改正法案は、どうも全面的な(もちろん右方向に「急進主義的」な)憲法改正を念頭に置いているようである。
これは、「日本国憲法の改正手続に関する法律案」14条1の「国会の発議に係る日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明…」というところからも想像がつくし、実際自民党の新憲法草案(PDF)を見てもかなり大幅な改変になっている。
自民党は戦後60年近く憲法が改正されてこなかったことが異常であると主張するが、逆に言えばここまで劇的な憲法改変を行った国というのはそう多いわけではない。
また、私は必ずしも憲法を変えることに反対ではないが、そこまでやるのであれば、ベネズエラが行ったように制憲議会(Constitutional Convention)を選出し、議論を尽くすのが自然なのではないかと思われる(ベネズエラが制憲議会方式を選んだ背景にはもちろん、通常の議会で反チャベス派が主流だったという事情もあるのだろうが、結果的にはより正統性の高い方式を選択することになっていると思う)。
憲法というものが本質的に立法の基盤になる以上、その制約を最も受けるのが立法権を司る議会である。
国民投票というプロセスを経るとは言っても、国会議員が自分たちの作業を律するルールを決めるということには違和感が残る(同様に、本来であれば憲法改正後は自らを選出した基盤が改変されるわけだから、両院は速やかに解散するべきであると考えるのが自然だろう)。
また、現実問題としても憲法問題のみを討議し、立憲後は速やかに解散する制憲議会は、相対的に見てクリーンで比較的公平性の高い議論を行うことが期待できるのでは無かろうか?
それと、憲法と「公共性(Public)」のコンセプトは切り離せない問題である。
自民党の改正案では「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に言い換えられている。
現行憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
自民党案第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
このことが含む法的な問題などはすでに各所で指摘されている。
例えば社民党の自民党「新憲法草案」批判(案)では次のように述べられている。
■市民の権利 ー公の秩序が許す範囲の「自由及び権利」これは、単なる言葉の言い換えではない。「公共の福祉」とはある人権が他人の人権と矛盾・衝突する場合の解決をはかるための調整、実質的公平の原理であり、人権に必然的に内在する制約である。これに対して、「草案」のいう「公益及び公の秩序」は、個人の権利を否定し個人を犠牲にした上での権力に対する忠誠を意味するものともなりかねないもので、外部から人権を制約するものと解される。現憲法が「侵すことの出来ない永久の権利」である基本的人権である「個人の自由と権利」が、明治憲法下での「人権保障」のような統治機構の定める秩序や法益の下位のものと位置づけられ、その許容範囲でしか存在できないものに貶められることになりかねないのである。
例えば国家の安全や、軍事目的といった公益のために、表現の自由や思想・信条の自由等が制限されることにつながり、戦争への批判を立法によって制限する根拠にもなりかねない。「草案」第9条2が自衛軍の任務として「公の秩序の維持のための活動」を規定していることからも、「公益及び公の秩序」が、軍事的要請をも含めた国家の求める秩序全般を指すことは明白である。
ここでは、こういった見解に基本的に賛同しつつ、こういった見解が成立してしまう歴史的・文化的背景について若干、考察してみたい。
英語の公共性に関する論文などで、「日本では、公共性は私益のアマルガム(混合体)ではなく、公と私という二つの領域があると見なされる」という記述が見られることがある。
逆に言えば、欧米圏の感覚では「公共性とは私益の混合物」なのである。
例えば、日本では井の頭公園で大道芸をする権利を地方自治体という「公」が大道芸人の「実績を審査し、許可を出す」ということが天下り的に許容される。
しかし、本来は静かな公園を望む「私益」と、賑やかな公園を望む「私益」の間をどのように調停するか、というのが公共性であり、規制はその公共性の結果にすぎない。
同様に、国家は市民の共有物であり、私的なものに先駆けて国家という公があるわけではない。
英語では国家に対して"Nation State"という語が当てられる。
これは、文字通り「民族の財産」という意味であり、元来「国家」が王の財産(Royal Estate)であったことに対して、国民(Nation)の財産になったということに由来する(「国」と呼んでいたのを国囲いに民という字に変えた、というイメージだと考えればわかりやすいだろう)。
ちなみにNationというのも、中世の大学で出身地域が一緒のグループが結成した同胞団をNatioと呼び習わしたことに由来するもので、元来極めて相対的なものである(例えばパリ大学ではフランス各地方についてそれぞれのNatioが存在する一方でイタリアについては単一のNatioが存在し、逆にボローニャの大学では…、という相対的な概念にすぎない)。
現在ではもっぱら英連邦のことを示すCommonwealthも、歴史的にはしばしば国家の意味で使われるが、これも同様に(文字通り)「共有の財産」を意味する。
こうした思想的前提のなかでは、全体主義的な思想はあくまで無理筋にすぎないし、逆に私的な利益を主張することは(それがあくまで事後の調整のための討議に開かれているという前提の上では)それがしかるべきプロセスの後に公益に資するという合意が生まれることになる。
一方で、公と私が二元論的にとらえられて、「貴方は公と私のどちらにつきますか?」と問われて、「私は私益を追求するのだ」と言い切るのは非常にハードルが高い(ホリエモンの日本社会に於ける新しさはこの言い切りにあったのかも知れない)。
また、微妙な混乱を招いているのは、「公」が国家に独占されていることである。
逆に、国家および地方自治機関以外のすべては「私」であり「民」であるとみなされる。
一方で、欧米語では公は「Public」であり、これは日本語の公よりもだいぶ広い言語である。
たとえばNPOは日本では「民間」だが、欧米ではPublicな組織である。
また、例えば「郵政民営化」といったような公共サービスの「民営化」は英語ではPrivatization (私有化)と表現される。
「民」がPoepleを指すものだとすれば、どちらかというと公的なものの領域に属する。
このあたりに留意すれば「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」の差異は明かであろう。
基本的に、「公」というのが、異なる私益を持つ集団の間の討議というプロセスを指すという欧米型民主制の理念に従ったものであるのか、民衆の外部に、その生活を規制するものとして存在するものであるのか(つまり明治以降の翻訳的な意味で使われているのか、江戸以前の伝統的な意味で使われているのか)明確にして論じていくべきであろう(その上で中世への回帰が好ましいという議論があるのであればそれもいいと思うのだが、そんな人はどの程度いるのだろうか?)。