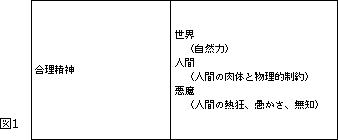
|
STS Network Japan '99 春のシンポジウム |
今回、「グローバル・サイエンス、ナショナル・サイエンス、ローカル・サイエンス」というタイトルでシンポジウムを企画したのは、科学が世の中のためになる、あるいは害になる、といったときに、果たしてその「世の中」というのはどんなものが想定されているのかを考えてみたいと思ったからであります。
例えば昨年秋に私は、議員連盟「科学・技術と政策」研究会のシンポジウムでのディスカッションをきくことができました。このときのことは最新号のニューズレターにも松原さんと私のレポートを掲載しましたので、なかにはお読みいただいた方もおられると思います。本日は同じものがお手元こ行っていると思いますが、もう一度そこでの議論の内容を簡単に振り返ってみたいと思います。
シンポジウムの発表者の方々が一貫して強調されたことは、我が国の科学技術の発展が世界に貢献しなければならないという側面と、そのことが国益にもかなうのであるという側面にがあることです。つまり、我が国は特に「サイエンス・ベース・テクノロジー」において世界のリーダーシップを取れるような貢献を行い、それによって世界的な政治情勢における発言力を増すと同時に、国内の経済も振興していく必要がある、というものです。
そうした立場に立つ論者の方々ですから、ニューズレターでの報告の中でも述べたとおり、国益の問題と世界(世界経済や第三世界)への貢献をあまり矛盾しないものとして語っていたと思うわれるのですが、それは、本当に矛盾しないものでしょうか? もちろん、科学技術が一国のためにのみあるのではないという認識があるのはよいことです。また、内田氏がハビビ・インドネシア大統領の言葉として、日本の企業はアジアからのインターンシップを受け入れることに欧米より閉鎖的だと語ったことからも判るとおり、たしかに「世界のためにも日本のためにもなること」で、まだまだ我が国にやれることはありそうではあります。しかし、はたして「誰のための」科学技術振興なのかを再考したとき、それらは矛盾を孕まないものとは言い切れそうにありません。
そんなわけで、今後の人類社会にとっての科学・技術の重要性は否定せずに、かつそれらの持つ価値をある程度突き放して客観的に検討できるような場が必要である、と考えたのです。
もちろん、科学・技術に対する世界的な期待も、議員連盟のシンポジウムで見られた見解と共通のものがあります。全米科学アカデミーのウェブに発表されたToward Grobal Scienceと題された記事の中で、科学者が「世界のいかなる場所でも」より合理的な政策決定のためにリーダーシップを握ることが必要であると論じています。この見解を端的に表しているのが冒頭で高らかに宣言される次のようなマニフェストです。
曰く「文化的価値の衝突や需要の競合に満ちた世界において、科学者達はどこにおいても、誠実さ、寛大さ、アイデアを由来と無関係に尊び、その一方で功績には報いるという、強力なコモン・カルチャーを共有している。NASの主要な目的は、科学者達と世界中にある彼らの組織との連帯を強めることである。我々のゴールは、国際的なディスコースにおける合理性の度合いを高め、その上意思決定のどんな状況でも科学者達の彼らの政府に対する影響力を強めつつ、国家間の相互交流において中心的要素となるような科学ネットワークを構築することである。」
ここでいくつか思いつく疑問はがあります。例えば、
・こうした期待を担う、また自らが担うと表明するような立場(つまり科学者共同体やその代表機関としての各国のアカデミーのことを指しているのですが)の歴史的、政治的バックグラウンドとはいかなるものなのか? これは果たして実際に影響力を持つ見解なのか?
・そして、今現在、現実に行われている科学・技術の研究開発活動は、こうした要請に応えられるようなものなのか? たとえばこの記事の中で言及されているような「世界の偉大なる知識の蓄積」とはいかなるものなのか? 果たしてそれは本当にグローバルなのか?
・また、この記事の中でもいくつか言及されているように、実際試みられた「科学の貢献」、つまり緑の革命を初めとする第三世界で行われた数々の実験(著者は謙虚にも今のところ「そのうちの少数は非常に成功したが、多くが失敗と判明している。」ことを認めているのですが)とはいかなるものであるのか。果たして我々はそういった試みにいかなる希望を託すことができるのであろうか?
この疑問のリストはまだまだ続くと思いますが、こうした疑問に答えを見つける試みは、先の疑問、つまり世界のための科学あるいはグローバル・サイエンスとは何か? それは国民国家の利益や地域性と矛盾しないものであるのか、という先ほど上げた疑問に答えを見つける助けになるのではないでしょうか?
と言うわけで本日は、多様な専門分野の方に講演を頂くことで、現代の科学・技術が置かれた具体的な状況を幅広くふまえつつ、こうした問題を考えていきたいと思います。
実際確かに、日本のためにも世界のためにもなることでまだまだやられていないことも数多くあるでしょう。しかしながら、この「世界」と日本や日本の企業の利益が一致しないような事態は、さらに多くあるはずです。このあたりの矛盾をごまかしてしまうことなしに、今後の科学技術のあり用を考えることは、大変重要であるはずです。
このことについて、少しだけお時間を頂いて、「科学・技術の受容者はだれか?」「それはどう析出できるのか」について、簡単に私見を述べさせていただきたいと思います。
さて、私は本来文化人類学を学ぶものでありまして、去年は小笠原諸島について若干の調査を行ったわけであります。小笠原諸島は行政区分上は東京都に属しますが、東京から1000キロはなれた太平洋の真ん中にあり、竹芝桟橋から船で26時間かかります。船は5日に一便ていど運航されており、現在のところ飛行場はありません。また、つい最近までテレビもBSしか入らない状態でありました。こうしたところでも、というよりも、こうしたところであればこそ、科学・技術の展開に大きな影響を被るというところもあるわけです。
例えば、飛行機の導入でも、長期的な環境を優先したい世代、つまり現象としては最近自然と非都会的な生活を望んで移り住んだ人々と、戦前からの居住者で、医者に頻繁にかかる必要があるような高齢者、および高齢者を抱えた世帯では、とうぜん意見が異なってくるわけです。
同様に、実はごく最近テレビもCSを利用して民放が移るようになったのですが、これも高齢者世帯と、(とくにテレビによって子どもの消費欲求が高まることを畏れる)若い世帯のあいだに断絶があります。
実は、このことが小笠原において顕著に現れるのは、そこが戦後30年以上にわたって米軍占領下にあり、一部の人々を除いて島への居住が許されていなかったため、(たまたま)戦前からの居住者世帯と、返還後移住した世帯が人々の知識としても、行政上の区分としても、可視的に分断されてしまっている、ということがあげられます。しかし、こうした対立は実は世界中に存在しているものだと思います。
その点から、本日のパネラーのみなさんの講演を私なりに解釈するための補助線にするという意味も込めて、科学をその利益受容者はだれかという視点から区分する、三つの理念系を提示してみたいと思います。
それは、プロレタリア科学、マイノリティー科学、サバルタン科学というものです。わたしはここで戦後の科学・技術の日常生活への影響力の増大を受けて、いま提示した順番で科学知識を理解するスキームが発生したと主張したいわけですが、あらかじめみなさんの注意を喚起したいのは、これが前段階を克服するような形で現れるたぐいのものではないと言うことです。つまり、現在においても必ずしもプロレタリア科学が有効性を失ったというわけではありませんし、こんごともそういう事態が起こるとも思いません。ただ、それだけでは不十分である、ということが主張されるだけです。このあたりの事情も徐々に説明していきます。
最初のプロレタリア科学という概念は、ある世代以上の人々にとっては比較的耳慣れたものだと想像します。しかし、もう一度現代的な視点から、この言葉がスローガン的に採用された事情を振り返ってみましょう。
我々は世界を善と悪の二元論で考えがちなものです。これは古今東西を問わず一般的なことではありましょうが、悪に何が入り、善に何が入るかについては、さほど一般性はありません。
すくなくとも戦後の一時期、あるいはもう少し古くから、西洋近代は、善の側に人間性、合理性、進歩、冷静さ、知識等を入れ、そして悪にその対立概念を入れてきました。そして、科学は悪に立ち向かう剣として重視されてきたのです。そうした総合的な理性を信じた人にバナールがいます。「バナールが論じたのは世界(自然力)、人間(人間の肉体と物理的制約)、そして悪魔(人間の熱狂、愚かさ、無知)という「合理的精神の三大敵」と戦って進歩するにはどうするか、であった」。この関係を図示すると、図1のようになります。
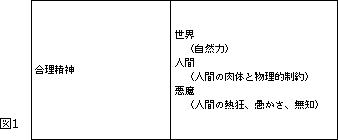
この時代においては、自然科学の領域に置いてはもちろんのこと、社会科学においてででもある「全世界に当てはまる法則があるし」、それらが無視されているのは「ある種の、主に社会・宗教的な偏見によるとしか思えない(カピッツア)」と論じることができたのです。
マルクス主義の伝統では、この時代精神はプロレタリアートという階級全体と同一のものであると論じられますから、ここではその伝統に従ってこれをプロレタリア科学と呼びます。換言すれば、プロレタリア全体が利益を享受できるような単一の科学が想定されていたわけです。
しかし、これは先ほど小笠原の例で私が示唆したように、いささかあやふやな仮定であることは現代では明白です。
実際、それは本当だろうかという疑いも、1960年代以降にはそんなに珍しいものではなくなってきました。60年代のカウンター・カルチャーは、これまでわるいとされたものをすべてよいものであると論じ、逆によいとされていたものをすべて悪だと論じました。
彼らがそれをおこなった背景として、我々は一つの事情を知る必要があります。つまり先ほどバナールのものとして掲げたリストには、通常明らかにされない暗黙の前提として、いくつかの項目が密かに続いていたのです。それをくわえたのが次の図です(これは単純な記号論、あるいは構造分析です。合理的精神という二項対立に、それが問題になる場に立ち現れる個々の要素、つまりそれが神話素とレヴィ=ストロースが呼ぶものに当たるわけですが、を割り振るわけです)。
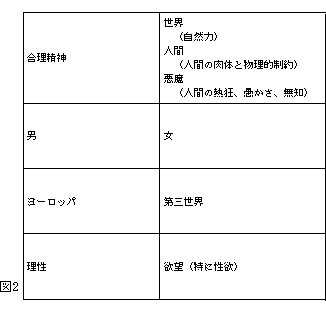
さて、こうした記号論において、劣位の項に置かれてしまったグループや個人の「名誉挽回」の方策はいくつか考えられます。
最初に行われたのが、実は劣位の項に見えるものはすべて(あるいは少なくともその一部は)優位の項に割り振られるべきものだったのだ、と主張することです。例えば、フェミニズムであれば、「論理的な女性もいた」とか「十分な教育を受ければ女性も論理的に振る舞える」と論ずるでしょう。
第二の方策は、実は劣位だと思われるのが本当は優位なのだ、という議論です。この革命的な視点は最初に性の研究の分野からもたらされました。マルクーゼ、ライヒといった論者は、フロイトの理論を援用して、理性とは自然な性や愛情のあり方の抑圧に他ならず、我々はそれを解放することによって真の自由と幸福を手に入れるのだ、というわけです。そして、60年代的な反科学のムーブメントはここを出発点に、図2の左側のすべてを否定し、右側のすべてを肯定した結果であったわけです。
これは同時に、ふつう右側の存在としてイメージされていたマイノリティー、例えばゲイ、ネイティヴ、女性と言った人々をエンパワーメントすることにもつながりました。このことは、革命が単一のものではなくて(つまり、すくなくともプロレタリアートといったような)単一の歴史的主体によって担われるのではなく、個々の歴史的背景によって目標とされるべき改革の意味が違う、ということも示していました。
たとえば、「むろん、世界中の飢餓に抗するたたかい、森林伐採の中止、核産業の無分別な増殖の停止といったような、統一的目標の決定を全面的には排除しない展望が必要であろう。ただ、その場合、他のさらに特異性を帯びた諸問題を無きがごとくに扱う、したってカリスマ的指導者の出現を必然化もする還元主義的な紋切型のスローガンは、もはや無用の物で無ければならないだろう。(フェリックス・ガタリ)」というような言い方がされるようになったわけです。
これを、エマニュエル・ウォーラスティンは、革命主義対改良主義、東西(自由主義対社会主義)、南北(先進国対第三世界)という地政学的対立に続いて現れた第三の対立軸であるとします。また、ウォーラスティンはこれをシステム対反システムという対立軸と呼びますが、これは現在多くの人が呼びならわしているように、モダン対ポストモダンの対立と呼ぶことも可能でしょう。この軸での対立は、しばしばオールド・レフトとニュー・レフトの対立という形でも現れます。近年各所で話題になっていたサイエンス・ウォーズもそうした流れの中でとらえられるべきでしょう。
さて、このマイノリティーを養護するような科学を、プロレタリア科学に対してマイノリティー科学と呼びたいわけですが、その中では当然、バナールのような「客観的な知」の無謬性は疑われます。それよりも言説実践的な側面でマイノリティーをグループとして立ち上げ、それを利益団体としてまとめ上げることが優先されるわけです。
こうした言説実践を可能にしたのはアメリカ型の文化相対主義、そしてフーコーとドゥルーズらによって担われた哲学です。
ここで注意したいのは、科学を「名指す」、科学知識の行為者とその受益者を指名しすることは、膨大で(かつおそらくその全容を知ることなど不可能な)人類全体の知識の、どの部分が発動するかを決定してしまうと言う意味で、言説実践であるといえるはずです。
そして近年、このマイノリティー科学的な立場に対して、自分がマイノリティーであることを主張して発言権を確保するようなアイディンティティ・ポリティクス(あるいは表象闘争)に陥って、世界に「政治的決定は不可能であるのだ」というニヒリズムの幻想を振りまいている、という非難があがるようになりました(こうした声を早くから表明し、かつて依拠したポストモダン的立場から撤退したテリー・イーグルトンのような人もいるわけです)。
その中で、マイノリティーの闘争という政治性を維持したまま、この問題を乗り越えようと言う試みが、現代のカルチュラル・スタディーズのなかで現れてきたサバルタン・スタディーズです。そのもっとも明確な理論的基盤として、アメリカの批評家ガヤトリ・スピヴァクの議論について、考えてみたいと思います。
スピヴァクは著書『サバルタンは語ることができるか』でマイノリティー研究批判を、その論理的基盤となっているフーコーとドゥルーズを批判することから展開し、デリダの脱構築を再評価することに次の段階への可能性を見ています。
さて、スピヴァックによるフーコー的な視点への批判を模式的に解説すると、以下のようになります。サバルタン、たとえば第三世界の女性、は二つの抑圧的な対立軸、つまり先進国-第三世界と男性-女性という対立軸により二重の抑圧を被っていることになります。これを次のような傾斜させたグリッドで表してみましょう(図3)。もし、第三世界の女性が世界システム内部での表象闘争において自分の位置を上げようとすれば、右上と同一化するか左上と同一化するか、つまり先進国の女性と同化して人権といったヨーロッパ的な道具立てのもとで戦うか、あるいは第三世界の男性と同化して伝統や文化的アイディンティティを武器とするかの二者択一をせまられると言うわけです。しかしながら、いずれにせよ女性はこのチェスゲームを斜めには進めません。先進国女性と同化したケースでは啓蒙訓化されるべき二流の市民として扱われ、第三世界の男性と同化したケースでは伝統に裏付けられた(それは創られた伝統なのですが)家父長制によって従属的な存在という扱いを受けてしまいます。ここにはヨーロッパ的普遍主義と反ヨーロッパ的土着主義の奇妙な共犯関係が成立しているのです。そのため第三世界の女性の声は、そのどちらかのコンテクストに還元されてしまい、けっしてフーコーが述べたような言説権力(の主体)を獲得することはなく、結果として権利集団としてのマイノリティー・グループを確立することもないのです。これが「サバルタンは語れない」ということです。
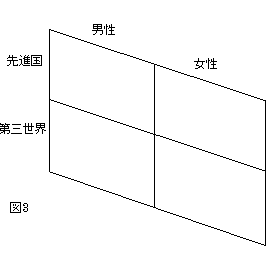
このとき、我々はウォーラスティンが述べるような地政学と、その中で近代合理主義や科学がしめる役割に常に注意をはらう必要が理解されるのです。つまりこれは、ウォーラスティンの3つの軸(革命主義対改良主義、東西、南北、システム対反システム、から東西を抜いたもの)の中で、合理主義や科学が、他の諸々の反科学的なものとの共犯関係の中で占めてしまう役割をとらえ、個別のエージェントや実践を、この構造の中から解放すること(脱構築すること)が求められると言うことでもあります。
最後にまとめれば、プロレタリア科学の領域においてのみ、我々はグローバルな科学を考えられるでしょう。しかし、それはマイノリティー科学を担う個々のエージェントによって介入され、限定されている、というのが現在の状況です。その対立を乗り越えるための試みというのは各所に存在しますが、決定的なものはまだありません(それがいずれは現れる、という楽観論にも懐疑的になる必要があるかも知れません)。そうした試みの一つとして、本日はサバルタン研究のさわりをご紹介したわけです。これが今日科学が普遍的であると(理論的にも実践的にも)認められない理由、そしてその無謬性の神話から、個別の知的実践を解放する、いわば科学の世俗化を求めることが重要である理由です。
参考文献
ウォーラスティン,エマニュエル 1991 『ポスト・アメリカ:世界システムにおける地政学と地勢文化』 丸山勝訳 藤原書店
ゴールドスミス,M. &A.マカイ 1969 『科学の科学』是永純弘訳 法政大学出版局叢書ウニベルシタス
スピヴァク,ガヤトリ・C 1998 『サバルタンは語ることができるか』上村忠男 みずずライブラリー