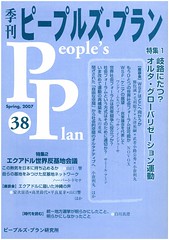Infomationの最近のブログ記事
RISTEXプロジェクトの一環としてご協力している西成高校で農場を活用したサイエンスカフェの試みを行います。
西成ジュニア・サイエンス・カフェは理科や科学に関心のある中学生や高校生が一緒実験や作業をいっしょにしながら、交流する試みです。
今回は大阪大学と連携した取組みを行います。テーマは『なにわの野菜が地球を救う』!
ゲストに松平尚也さん(プロフィールは裏面)を迎えて、私たちの身近にある「なにわの野菜たち」が世界的な社会問題である「地球温暖化」と、どんな関係があるのか?を考えてみます。
▼松平さんからのメッセージです。
「フードマイレージ」っていう言葉聞いたことあります? 「食べモンの(=food) 輸送距離(=mileage) 」という意味。食べ物の生産地と消費地が近ければ、フードマイレージは小さくなって、遠くから食料を運んでくると大きくなる。遠くから運んでくるとエネルギーを使ったり、二酸化炭素(CO2)を排出するので温暖化が進む中で近くで作られた食べモンを食べましょうという意味やねん。
大阪の食料自給率はなんと2%。食べモンの多くは他府県か海外から来てる。
でも実は大阪にもジモトの野菜があって、これがおいしくて体にいいだけでなく、温暖化も止める役割がある。その野菜は「なにわの伝統野菜」。天王寺蕪、田辺大根、河内一寸そら豆といろいろある野菜から世界の食料の話まで一緒に考えまひょ。
日 時: 08年12月13日(土)10時〜12時 ※雨天でも実施します。
場 所: 大阪府立西成高等学校農場及び化学実験室
内 容: 【交流】 テーマ 『なにわの野菜が地球を救う』
1 ゲストと参加者がテーマについて話しあう
2 西成高校農場で「なにわの野菜」の種をまく (予定)
持参物:筆記用具
申 込: 梅南中学の生徒は龍神先生まで申し込んでください。
西成高校の生徒は坪庭先生まで申し込んでください。
地域の方は西成高校の教頭(三上)まで申し込んでください。
連絡先:大阪府立西成高等学校 西成ジュニア・サイエンス・カフェ事務局
電話(06)6562−5751 FAX(06)6561−3028
メールアドレス k−mikami[at]nishinari.osaka−c.ed.jp (※[at]を@に変えてください)
*メールで申し込まれる場合は、お名前・連絡先をお知らせください。
※(独立行政法人)科学技術振興機構サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト事業
※(国立大学法人)大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 共催事業
松平尚也(まつだいらなおや)さん
AMネット代表理事。アジア農民交流センター世話人。
京都自由学校で縁農講座を企画。京都京北で農業に携わりながら現場の視点を生かして食や農そして水の循環について考え、調査し発信している。1998年から4年間は京都市中央卸売市場鮮魚で働く。グローバル化と水産・漁業の現場を実践的に調査。 2003年世界水フォーラムが京都で開催された折には市民ネットワークに関わり、桂川上下流交流事業に携わった。その時に出会いがきっかけになり桂川の袂に移住。現在六反の田畑を伝統野菜を作付し未来の食や農業について考える毎日を過ごす
※(独立行政法人)科学技術振興機構
サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト事業
※(国立大学法人)大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 共催事業
▼これまでの西成ジュニア・サイエンス・カフェ
【第1回】10月11日(土)
《実験》 西成高校農場と梅南中学農場の土を比較してみよう
1 土のなかの微生物を観察する
2 土のなかの養分を測定する
3 みんなで「焼きイモ」を食べる
【第2回】11月22日(土)
《実験》 土の持っている力を実感してみよう
1 西成高校農場の土壌を比較実験が可能なように改良し、それぞれに作物を植
え付ける。
2 西成高校農場の土のなかの微生物を観察する
3 みんなで「焼きイモ」を食べる

大阪大学CSCDの紀要、『Communication-Design』 [1] 異なる分野・文化・フィールド - 人と人のつながりをデザインするが大阪大学出版会から発売されました。
私に関係したものとしては「科学技術コミュニケーション演習プログラムの開発 CSCD方式の提案」(八木絵香さん、小林傳司さんとの共著)と「サイエンスショップにできること 多元化する社会で大学に求められているもの」(単著)の二報が掲載されています。
また、中川智絵さんらの「サイエンスショップ猪名川・藻川プロジェクト中間報告」は上記サイエンスショップ論文と関係が深いので、併せてお読みくだされば幸いです。
Communication-Design [1] 異なる分野・文化・フィールド-人と人のつながりをデザインする
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 
大阪大学出版会 2008-07-24
売り上げランキング :
Amazonで詳しく見る by G-Tools
ちなみに明日、土曜日の早朝には、以下のイベントのため、大阪に戻ります。
第4回柏原東ジュニア・サイエンス・カフェ 「食品リスクを計測する 2」 http://cscd.osaka-u.ac.jp/activity/view/127ジュニア・サイエンス・カフェは、高校生が中心となってテーマや質問項目を決め、お茶を飲みお菓子を食べつつ、くつろいだふんいきの中で、しろうとが専門家と科学について話し合う集まりです。
第4回の今回は、第3回に引き続き、現在、人々の関心の高い「食品の安全」について考えます。今回は特に、食品の安全性を「科学的に」検証するというのはどういうことなのか?、またそのための社会的な仕組みはどうなっているのかなどについて、社会との関係(学問分野としては科学哲学や科学技術政策)の視点から議論していきたいと思います。会場:大阪府立柏原東高校
http://www.osaka-c.ed.jp/kashiwarahigashi/map/map.htm
日程: 2008年02月23日(土) 13:30〜15:30 (13:00会場)
専門家: 神里達博(東京大学 特任准教授)
司会進行: 柏原東高校理科クラブ
主催:大阪府立柏原東高校(教師コーディネーター 平井俊男)
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター■専門家プロフィール
1967年生まれ、神奈川県出身。東京大学工学部卒、同大学院総合文化研究科・博士課程単位取得。科学技術庁(行政官)、三菱化学生命科学研究所、社会技術研究開発センターを経て、現職。専門は、科学史・科学論。朝日新聞論壇時評・合評委員。著書に『食品リスク−BSEとモダニティ』弘文堂,2005.など。
■問い合わせ窓口
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 春日匠(かすが しょう)
tel/ 06-6816-9494 fax/ 06-6875-9800
e-mail/ stc[at]cscd.osaka-u.ac.jp([at]を@に変えてください)■申し込み方法
中学生以上なら、どなたでも参加いただけ、参加費は中学生と高校生は無料です。
今回から、大学生以上は茶菓代として300円かかります。御協力、お願いします。
FAXないしメールに「第1回柏原東高校ジュニア・サイエンス・カフェ参加希望」と明記の上、お名前と連絡先(メールアドレス、電話番号ないしFAX番号)を明記して上記連絡先までお申し込みください(お電話でのお申し込みはお受けできません)。
日程等に変更のない場合はお申し込みにお返事はいたしませんので、当日会場までお越しください。※本企画は、(独)科学技術振興機構(JST)「研究者情報発信活動推進モデル事業」に採択された受託研究の一環として行っています。
PDF版チラシは
http://cscd-stc.weblogs.jp/blog/files/CSCD080223.pdf
からダウンロードして頂けます。
昨日、成田から帰ってきたばかりでバカみたいですが、明日のイベントのため、上京します(まぁ、成田は東京じゃないってことで…)。
詳細は以下のとおり。
==========================
CSCDpresents「知デリ」in アップルストア
〜アート&テクノロジー:知術研究プロジェクト〜
==========================
ロボットとケダモノとニンゲン 〜ホントに区別がわからない〜科学技術・哲学・アートなど多分野の専門家で構成される当センター(CSCD)では、“コミュニケーションデザイン”という未知なる主題の実践的研究のために、「知術」というテーマを掲げ、その定義・意味や有用性について考察する「知術研究プロジェクト」を2006年度に始動しました。
このプロジェクトでは、さまざまな領域で活躍される方々と対話の機会を設け、各々の専門分野における「知識」や「技術」を参加者の方々と横断・交換することを通して、新しい発想の創出やアイデアの実現に繋げることを目指しています。
大学と社会が連携して、「知術」を人々に還元(デリバリー)するトークプログラム、通称「知デリ」です。
今回のタイトルは、、、。
ロボットとケダモノとニンゲン〜ホントに区別がわからない〜
世界の天才100人に挙げられる(※)アンドロイド・ロボット研究の第一人者と、現代美術家・ペットショップオーナー・演出家と多岐に渡る活動で異彩を放つアーティストが、他者との関わりについて語らいます。
この試みにご注目下さい。
(※)Synectics社(英)の調査「世界の100人の生きている天才のランキング」
■東京開催
日 時:2008年2月22日(金)18:00-20:00ゲスト:飴屋 法水(演出家・美術家)
石黒浩(知能ロボット学者/大阪大学大学院教授)
ホスト:平田オリザ(劇作家・大阪大学CSCD教授)
定 員:150名(入場無料/当日先着順/立見含む)
会 場:アップルストア銀座 3Fシアター
東京都中央区銀座3-5-12サヱグサビル本館 TEL:03-5159-8200
東京メトロ「銀座」「銀座一丁目」JR「有楽町」
のいずれかを下車、中央通り松屋向かい
http://www.apple.com/jp/retail/ginza/map/■ ゲスト プロフィール ■
飴屋 法水/あめや のりみず(演出家・美術家)
1961年生まれ。78年、唐十郎主催の「状況劇場」に参加。84年「東京グランギニョル」を結成し、カルト的な人気を博す。87年「M.M.M」を立ち上げ、メカニックな装置と肉体の融合に よ る「スキン/SKIN」シリーズでサイバーパンク的な舞台表現を固 める。90年代は舞台から美術活動に移行。コラボレーション・ユ ニット「TECHNOCRAT」の一員として血液、精子、菌などを用いた 作品を制作。95年、ヴェネツィア・ビエンナーレに「パブリック ザーメン」で参加するが、その後美術活動を停止。同年、ペットショッ プ「動物堂」を開設。2005年「バ ング ン ト」展で美術活動を再開。昨年、平田オリザ作「転校生」の演出を手がけ、本格的な表現活動に期待が集まる。著書に「キミは珍獣(ケダモノ)と 暮らせるか?」(文春文庫) などがある。石黒浩/いしぐろひろし(知能ロボット学者/大阪大学大学院教授)
1963年生まれ。大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。2003年より同大学院工学研究科知能・機能創成工学専攻 知能ロボット学研究室教授。 ATR知能ロボティクス研究所客員室長。社会で活動できるロボットの実現を目指し、知的システムの基礎的な研究を行う。これまでにヒューマノイドやアンドロイド、自身のコピーロボットであるジェミノイドなど多数のロボットを開発。また、ロボカップ世界大会にTeamOSAKAとして参戦し、4度の優勝を果たす。主な著書に「アンドロイドサイエンス ~人間を知るためのロボット研究~」(毎日コミュニケーションズ)。共著に『コミュニケ−ションロボット』(オ−ム社)、『知能の謎』(講談社)、「爆笑問題のニッポンの教養ーロボットに人間を感じるとき」(講談社)などがある。■ ホスト プロフィール ■
平田オリザ (劇作家・大阪大学CSCD教授)
劇作家、演出家、劇団「青年団」主宰、こまばアゴラ劇場支配人。2000年、桜美林大学文学部助教授を経て、2006年よりCSCD教授。著書に「演劇入門」講談社現代新書、「芸術立国論」集英社新書、「対話のレッスン」小学館など多数。「東京ノート」で岸田國士戯曲賞、「月の岬」の演出で読売演劇大賞最優秀作品賞、「その河をこえて、五月」で朝日舞台芸術賞グランプリ等受賞歴多数。主催:大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)
企画:CSCDワーキングメンバー
(小林傳司 木ノ下智恵子 久保田テツ 春日匠 仲谷美江)
共催:アップルストア銀座
協力:NPO recip [地域文化に関する情報とプロジェクト]問い合わせ
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)
大阪府吹田市千里万博公園1-1
TEL:06-6816-9494 FAX:06-6875-9800
http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/
※本イベントは平成19年度JST地域科学技術理解増進活動推進事業「調査研究・モデル開発」の補助による活動です。
※PDF版ちらしは以下のURLからダウンロードいただけます。
http://cscd-stc.weblogs.jp/blog/files/CSCD080222.pdf
第三世界債務の問題に取り組むNGOであるCADTMベルギーの代表エリック・トゥーサンが来日します。トゥーサンは昨年誕生したエクアドル大統領ラファエル・コレアの顧問にも就任、コレアがベネズエラ大統領ウゴ・チャベスらと、世界銀行の代替案として推進している「南の銀行」の実現にも力を尽くしています。
今回、ATTACなどの社会運動団体が中心となってトゥーサンの講演会を企画しています。分散型ネットワークなので、特に共通の「公式サイト」的なものがないのですが、それでは不便だということもあって、ATTACのドメイン内にそれっぽいものをつくっておきました。告知などのさいにはご利用ください。
◎小さな国 エクアドルの大きな挑戦
小さな国 エクアドルの大きな挑戦 債務と貧困からの脱出のために 〜エリック・トゥーサンさんとセサル・サコットさんを迎えて〜日時: 2007年12月17日(月) 18:00
場所: 大阪市立大学文化交流センター
(大阪市立大学梅田サテライト 大阪駅前第二ビル6階)
主催 「小さな国 エクアドルの大きな挑戦」実行委員会
協賛 大阪市立大学大学院創造都市研究科問い合わせ:
ATTAC関西グループ tel 06-6474-1167(喜多幡)
kitahata@ss.iij4u.or.jp
(特活)関西NGO協議会 tel 06-6377-5144
knc@ak.wakwak.com
●なぜエクアドルなの? どういう話しが聞けるの?
エクアドルは南米大陸の左肩にちょこんと乗った小さな国。
「エクアドル」とはスペイン語で「赤道」の意味です。
大変多織で豊かな自然に恵まれたながらも、国民の4人に1人が極貧状況、不完全失業率は40%に及び、何十万人もの人々が国を離れ、遠く米国やヨーロッパに出稼ぎに行く状況です。
その中で昨年11月、弱冠43歳で大統領に選出されたラファエル・コレア氏が今、新風を巻き起こしています。その極貧状況を生み出しているのが債務問題、つまり借金です。
多くの発展途上国は依然として豊かな国や国際機関等から多くの借金をしており、そのお金は民衆の為ではなく環境破壊に繋がるプロジェヲ卜や独裁的な政治家もしくは企業の儲けになってる事が多く、毎年国家予算のなんと30〜50%にも及ぶ債務支払いに苦しんでいます、その為に削られる予算はまず国民の医療、教育、環境保全といったものです。エクアドルではこの新しい大統領の政府が自ら民衆の側に立って「不当な債務の支払い拒否』を打ち出しました、これは非常に画期的です。
そして日本はこのエクアドルの債務の相手国、第3位の国なのです。
彼等の貧困の上に私達の生活が成り立っていると言っても過言ではありません。そこで今回は債務問題にお詳しく日本でも著書が好評のエリック・トゥーサンさんと
エクアドルの活動家、セサル・サコットさん、エリックさんの著書を翻訳されたジュビリ一九州の大倉純子さんをお招きし、現地の生の声をお伺いします。債務問題等にお詳しい方は勿論、お金の問題になると難しそうと、これまでちゃんと知る機会のなかった方にも非常に貴重な機会と思われます。
なぜ途上国が債務漬けになったのか?
なぜ返す事が出来ないのか?
はじめに債務問題についての初歩的なレクチャーを行います、
どなたも安心してご参加ください!
 | 世界の貧困をなくすための50の質問―途上国債務と私たち ダミアン ミレー エリック トゥーサン Damien Millet 柘植書房新社 2006-05 売り上げランキング : 95980 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
それと、世界社会フォーラム2008(1月26日世界同時行動)の日本語ウェブサイトも出来てますね。
世界社会フォーラムのためにナイロビ(ケニア)に行ってきたわけですが、そのとき、ノーベル平和賞(2004)受賞者ワンガリ・マータイ氏の創設したNGO、グリーンベルト・ムーブメントの主催するツアーに行ってきましたが、そのときの報告を『季刊ピープルズ・プラン』No.38に載せました。
まだAmazonでは買えないようですが、楽天booksでは購入できるようなのでお知らせ。
…ところで、このウィキペディアがライトライヴリーフッド賞にあたえている翻訳「正しい生計賞」は酷いなぁ。といって、上手い翻訳も思いつきませんが…。「明るい生活賞」もヘンだしねぇ。
P.S.
Amazonでも買えるようになったようです。
NPO法人サイコムの理事として、大阪大学21世紀COE「インターフェイスの人文学」公開講座 科学技術と倫理 でしゃべります。
以下、予告みたいなものです。
20世紀を、科学技術は人類の生活に必須のものとなりました。しかし、その間一貫して規模の拡大を続けた研究開発という営みは、今成長の限界に来ています。こうしたなか、科学技術が社会の要求に十分答えていないという不満も無視できない問題であると言えるでしょう。ここでは、サイエンスショップと呼ばれるシステムを事例として、科学者や大学が社会の求めるものを上手く組み上げられるようにするとともに、自分たち自身を活性化させることができないか、考えてみたいと思います。
「市民の方のご参加・来聴歓迎致します(無料。手続き等不要)」とのことですので、大阪大学の誇る中之島センターを覗いてみたい方は是非どうぞ。
詳細は以下の通りです。